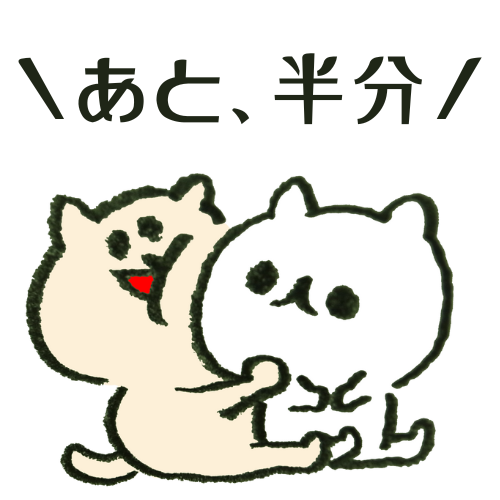この記事の解説音声

Google SEOランキング要因200以上
音声で聞くのもわかりやすいです!
Googleの「200以上のランキング要因」について
もはや都市伝説に近いくらいの感覚で「SEOには200以上のシグナルがあるらしい、、」と囁かれているのですが、Nishant Nischalさんの記事をとgoogleの公式アナウンスを元にに日本人向けにまとめてみました。
【ドメイン関連】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| ドメイン年齢 | 取得してから何年経っているか。古いほど信頼されやすい。 | ドメインはなるべく長く保有・運用を継続する。 | 高 |
| 登録期間の長さ | 長期間で登録されていると長く運用されるサイトと見なされる。 | 2年以上の長期でドメインを登録更新する。 | 中 |
| 有効期限 | 有効期限が切れるとサイトも消えやすいと判断される。 | 有効期限が切れないよう自動更新を設定する。 | 高 |
| ドメイン履歴 | 過去に問題のあったドメインは順位に悪影響が出ることがある。 | 新規取得時は中古ドメインの履歴を調査。ペナルティ歴のないものを使う。 | 高 |
| 完全一致ドメイン | 検索キーワードと全く同じ文字列のドメイン名。 | 必要に応じて活用。ただし中長期的にはブランド性も意識する。 | 中 |
| 部分一致ドメイン | キーワードの一部を含むドメイン名。 | メインキーワードを含めて取得するのも有効。 | 中 |
| ドメイン名にキーワードを含むか | 重要キーワードが入っているとSEO上有利になることがある。 | サイトテーマに合うキーワードを含めると良い。 | 中 |
| ドメインオーソリティ | ドメイン全体の信頼度や権威性。 | 長期運用・良質な被リンク獲得に努める。 | 高 |
| トップレベルドメイン | .comや.jpなど末尾の種類。信頼性や地域性に影響。 | 日本向けなら .jp や .com、信頼されやすいものを選ぶ。 | 中 |
| ドメインの信頼性 | Googleからどれだけ信頼されているか。 | 品質の高い運用を継続し、過去に問題を起こさない。 | 高 |
| 国別ドメイン | .jp(日本)や.uk(イギリス)など、国ごとのドメイン。 | 日本国内向けサイトは .jp 取得がベスト。 | 中 |
| ドメインの人気 | 多くのサイトからリンクされているか。 | 被リンク対策やPRで自然な人気を積み上げる。 | 高 |
| ドメインがテーマと関連しているか | ドメイン名や内容が、ジャンル・テーマと一致しているか。 | ブランド名や主要キーワードでテーマが伝わる名前に。 | 中 |
| ドメイン名の長さ | 短くて覚えやすいほど有利。 | なるべく短く、シンプルなものを選ぶ。 | 中 |
| ドメインの評判 | 他のサイトやSNSでの評価・口コミ。 | ネガティブな情報が広まらないよう管理。 | 高 |
| 過去のペナルティ歴 | 検索エンジンから過去にペナルティを受けていないか。 | 取得前に履歴を調査し、怪しいものは避ける。 | 高 |
| サブドメインの使用 | blog.example.comのような活用状況も評価に影響。 | 必要に応じて本体サイトとの関連性を保つ。 | 低 |
| ドメイン登録情報のプライバシー | Whois情報が非公開だとスパム判定を避けやすい。 | プライバシー保護オプションを活用。 | 低 |
| ドメインレベルのリダイレクト | 古いドメインから新ドメインへの転送がSEOにプラス。 | 301リダイレクトを正しく設定する。 | 高 |
| 複数ドメインからの被リンク | いろんなドメインからリンクをもらうと信頼度アップ。 | 多様なサイトからナチュラルリンクを集める。 | 高 |
| DNSサーバのパフォーマンス | 管理サーバの応答速度が遅いとSEOにマイナス。 | 安定・高速なDNSサービスを利用。 | 中 |
| ドメインメールの使用 | 独自ドメインメールを使うと信頼性が高く見られる。 | info@自社ドメイン等のメールを利用。 | 低 |
| ドメインが初めて被リンクされた時期 | 外部から初めてリンクされた日が古いほど信頼されやすい。 | 早い段階から外部サイトに取り上げてもらう。 | 低 |
| ドメインの新しさ | 取得して間もないドメインは評価が低いことが多い。 | 新規ドメインは時間をかけて実績を積む。 | 中 |
| 過去の被リンク推移 | 時間をかけて自然に増えたリンクが多いほど評価。 | 急激なリンク増は避け、継続的に獲得する。 | 高 |
信頼されるドメインを育てるには、コツコツと質の高い情報発信を続け、継続してサイトを運営することが一番の近道です。
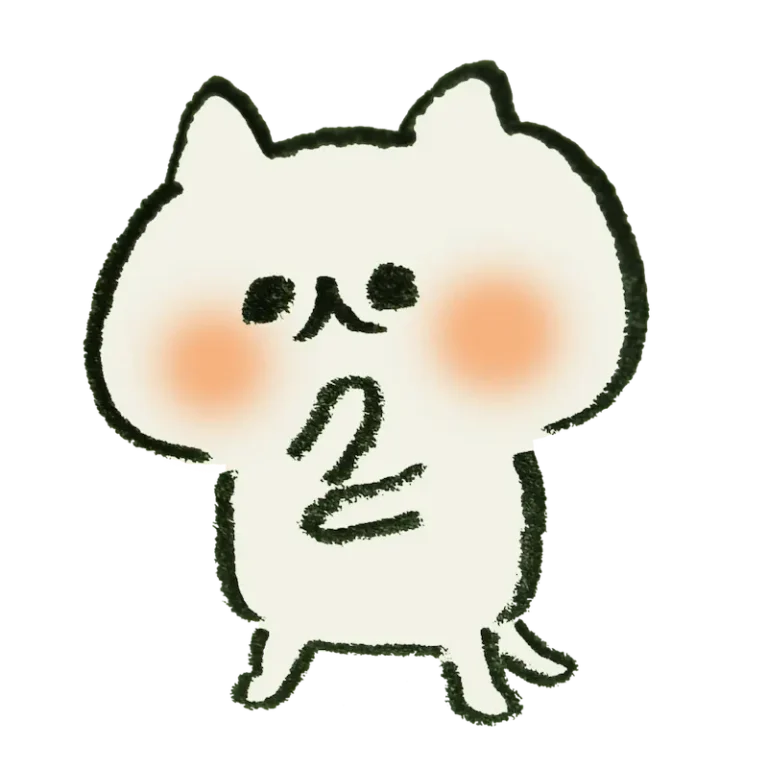
【サイト全体関連】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| SSL証明書(HTTPS) | サイトが安全な通信(https)で守られているかどうか。 | サイト全体をhttps化(SSL導入)。 | 高 |
| サイト構造(ナビゲーション・シロ構造) | メニューや階層が分かりやすく整理されているか。 | 階層を整理し、迷わないナビゲーションにする。 | 高 |
| XMLサイトマップ | サイト全体のページ一覧を検索エンジン向けにまとめたファイルがあるか。 | サイトマップを自動生成・Googleに送信。 | 高 |
| robots.txtの有無 | 検索エンジンに「どのページを見て良いか」を指示するファイル。 | robots.txtを正しく設置・管理。 | 高 |
| サイトの速度 | ページの表示が速いほど、順位や満足度が上がる。 | 画像最適化、キャッシュ、サーバ強化。 | 高 |
| 内部リンク構造 | サイト内ページ同士がうまくリンクでつながっているか。 | 関連記事・回遊を意識した内部リンク設計。 | 高 |
| モバイル対応 | スマホやタブレットでも見やすく操作しやすいか。 | レスポンシブデザイン導入。 | 高 |
| サイトセキュリティ(脆弱性チェック) | ハッキングされにくい安全な作りになっているか。 | セキュリティ対策プラグイン導入・更新。 | 高 |
| カノニカルタグの使用 | 「本来評価されるべきページ」をGoogleに伝えているか。 | canonicalタグで正規ページを指定。 | 高 |
| パンくずリストの有無 | 現在位置が分かる「パンくずナビ」設置の有無。 | パンくずリスト設置・構造化データ化。 | 中 |
| 構造化データ(マイクロデータ、JSON-LD) | 検索エンジンに内容を正確に伝える“おまじない”。 | Schema.orgなどで構造化データ追加。 | 高 |
| AMP(モバイル高速表示) | スマホで瞬時に表示される特別な仕組み。 | 必要な場合のみAMPを導入。 | 低 |
| リンク切れがないか | サイト内に壊れたリンクがないか。 | 定期的なリンクチェックと修正。 | 高 |
| クリーンなURL構造 | URLが短く、わかりやすい表記になっているか。 | 短くシンプルなURL設計・日本語URL回避。 | 中 |
| サイトのクロール容易性 | Googleがサイトの全ページを見つけやすい作りか。 | クロールブロックを避け、リンク切れ修正。 | 高 |
| ドメインレベルのSSL | サイト全体でSSL(https)が有効か。 | すべてのページでhttps化を徹底。 | 高 |
| パンくず構造化マークアップ | パンくずリストを構造化データで記述。 | Schema等で構造化データ記述追加。 | 中 |
| リダイレクトチェーンの管理 | 多重リダイレクトがないよう整理。 | 不要なリダイレクトを減らす。 | 中 |
| 適切な301リダイレクト | ページ移動時は301リダイレクトで案内。 | 移転時は301で統一。 | 高 |
| ページネーションの実装 | 記事一覧などの分割表示が適切か。 | rel=”next/prev”やUI設計見直し。 | 中 |
| サイト内検索機能 | サイト内に検索ボックスがあるか。 | サイト内検索を実装(WPなら標準でOK)。 | 低 |
| コンテンツ重複の管理(rel=canonical) | 重複ページでも評価を一つにまとめているか。 | canonicalタグで重複排除。 | 高 |
| サーバーの所在地(ローカルSEO) | サーバーが日本国内など地域に合っているか。 | 日本向けは国内サーバーを選択。 | 低 |
| meta robotsタグの活用 | 各ページでインデックス指示が適切か。 | noindex等のタグを正しく設定。 | 中 |
| ユーザーフローに沿ったサイト設計 | 目的に迷わずたどり着けるサイト設計か。 | カスタマージャーニー設計・導線改善。 | 高 |
訪問者も検索エンジンも迷わない、分かりやすい構造や動線づくりを意識しましょう。
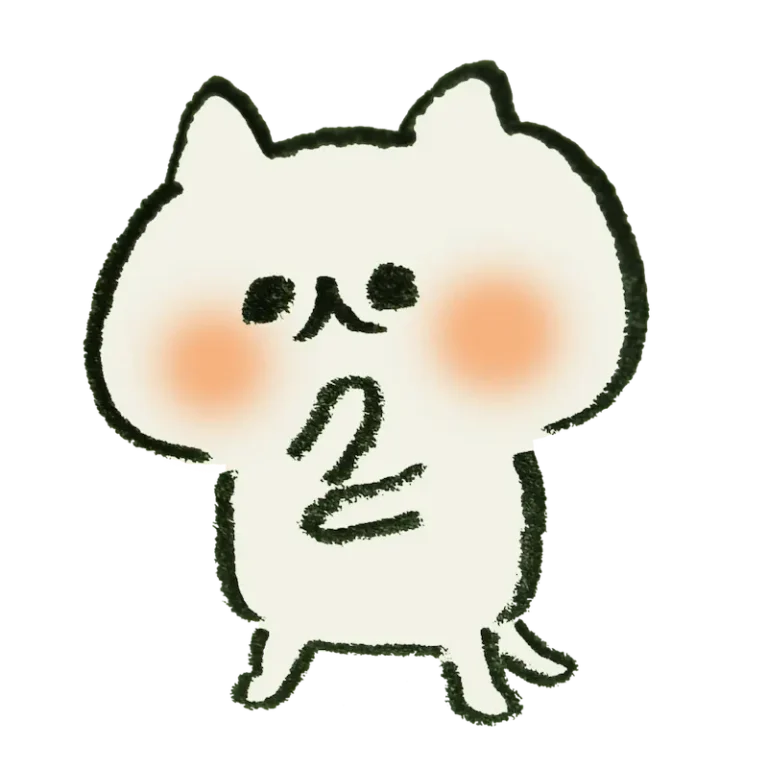
【ページ関連】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| コンテンツの質 | 役立ち、分かりやすく信頼できる内容か。 | 読者の悩みを深く解決する独自性ある記事を書く。 | 高 |
| コンテンツの長さ | 必要な情報が十分に書かれているか。 | 網羅的な情報提供と適切な分量に調整。 | 高 |
| タイトルタグ内のキーワード | タイトルにキーワードが入っているか。 | 狙いたい検索キーワードを含める。 | 高 |
| URL内のキーワード | URLにキーワードが含まれているか。 | 英語でシンプルなURL+主要ワード使用。 | 中 |
| メタディスクリプション内のキーワード | 説明文にもキーワードが含まれているか。 | キーワードを自然に入れて魅力的な説明に。 | 中 |
| 見出しタグ内のキーワード | 見出しにもキーワードが入っているか。 | H2/H3にもターゲットワードを使う。 | 高 |
| キーワード密度 | 多すぎず少なすぎず自然な回数で使われているか。 | 読みやすさ優先で自然な執筆を心がける。 | 中 |
| コンテンツの更新頻度 | 新しい情報にアップデートされているか。 | 定期的な見直しと最新情報の追加。 | 高 |
| ユーザー体験(可読性、レイアウト) | 読みやすく、使いやすいレイアウトか。 | フォントや余白、箇条書き活用など。 | 高 |
| マルチメディア | 写真や動画などを使って分かりやすくしているか。 | 画像・図解・動画を適切に挿入。 | 中 |
| 内部リンク | 他ページへのリンクが自然につながっているか。 | 関連記事への内部リンクを設置。 | 高 |
| ページ読み込み速度 | ページが素早く表示されるか。 | 画像圧縮・キャッシュ活用。 | 高 |
| モバイル対応 | スマホでも快適に読めるか。 | モバイルレスポンシブに最適化。 | 高 |
| コンテンツの関連性 | 内容がページのテーマと合っているか。 | タイトルと本文の整合性を重視。 | 高 |
| 画像最適化 | alt属性や無駄に大きな画像を使っていないか。 | altテキスト記述・画像圧縮。 | 中 |
| 構造化データ | 検索エンジンに内容を正しく伝えるコードが使われているか。 | FAQ・記事タイプなどスキーマ追加。 | 高 |
| 外部リンクの質 | 信頼できる他サイトへのリンクを貼っているか。 | 権威あるサイトや出典元へリンク。 | 中 |
| ページの階層 | トップページから何回クリックで行けるか(浅い方が良い)。 | 2クリック以内を目指すサイト設計。 | 高 |
| コンテンツの独自性 | 他と同じ内容になっていないか。 | コピーではなく自分の言葉・体験を重視。 | 高 |
| 文法・スペルミス | 誤字脱字や文法ミスがないか。 | 執筆後に校正チェックを徹底。 | 中 |
| H1タグ内のキーワード | 一番上の見出し(H1)にキーワードが入っているか。 | 記事タイトルにメインKWを明記。 | 高 |
| コンテンツの形式 | 箇条書きや小見出しで整理し、読みやすいか。 | 箇条書き・ボックス・表などを活用。 | 中 |
| ページオーソリティ(PA) | ページ自体の信頼度や評価。 | 良質な被リンク・SNS拡散で評価UP。 | 高 |
| ソーシャルシェア数 | SNSでどれだけシェアされているか。 | シェアボタン設置・拡散施策実施。 | 中 |
| クリック率検索結果が表示された回数のうち、クリックされた割合(CTR検索結果が表示された回数のうち、クリックされた割合) | 検索結果でクリックされる割合。 | タイトルと説明文を魅力的に工夫。 | 高 |
| 滞在時間 | ページがどれくらい読まれているか。 | 滞在したくなる読み応えを目指す。 | 高 |
| 直帰率 | ページだけ見て離脱する割合。 | 関連記事や動画で回遊を促す。 | 高 |
| 自然言語(会話的な表現) | 会話のような分かりやすい表現か。 | 固い表現より自然な語り口にする。 | 中 |
| モバイルファーストインデックス | Googleはスマホ表示を基準に評価する。 | モバイルでの見え方を最優先でチェック。 | 高 |
| アンカーテキストの質と関連性 | リンクに使う文字が内容に合っていて分かりやすいか。 | “こちら”より「〇〇の詳細」など具体的なリンク文。 | 中 |
1ページごとに「誰のどんな悩みを解決したいか」を明確にし、内容に一貫性を持たせつつ、「わかりやすく」「つかいやすく」を意識しましょう。
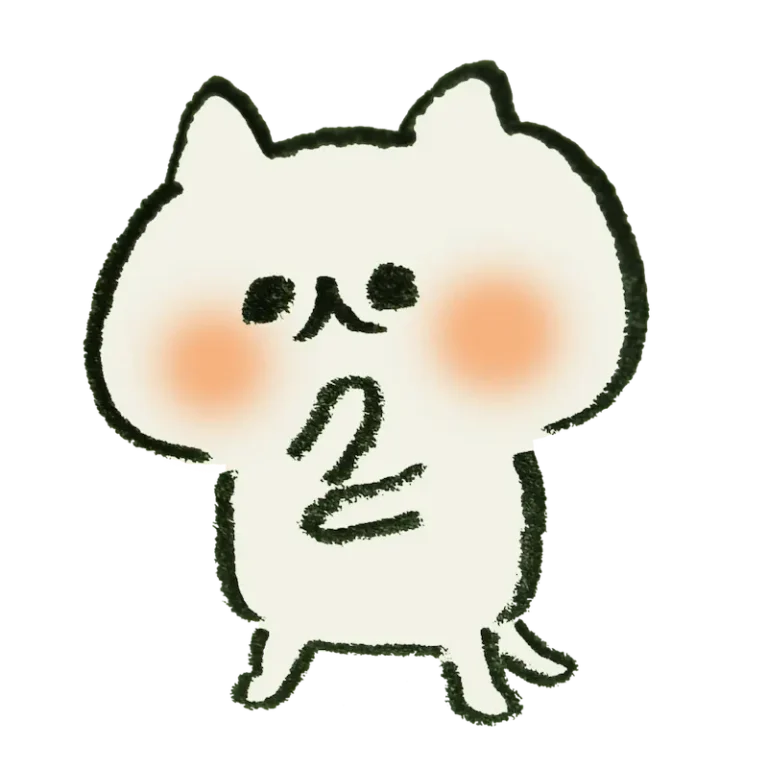
【被リンク関連】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 被リンクの質 | 信頼できる有名サイトからのリンクは評価が高い。 | 権威性・関連性の高いサイトからナチュラルリンクを獲得。 | 高 |
| 被リンクの量 | たくさんリンクされているサイトは人気・信頼性があると見なされる。 | コンテンツ拡散や広報活動で多くのリンクを得る。 | 高 |
| 被リンクの関連性 | 内容が似ているサイトからのリンクほど効果が大きい。 | 業界やテーマが近いサイトからリンクをもらう。 | 高 |
| 被リンクのアンカーテキスト | リンクに使われている言葉が自然で内容に合っているか。 | キーワードを自然に含めたアンカーを意識。 | 中 |
| リンク元ドメインの権威性 | 大手や信頼性の高いサイトからのリンクほど価値が高い。 | マスコミ・行政・教育機関などの露出も狙う。 | 高 |
| バックリンクの多様性 | 色々なサイトからリンクされているか。 | 分野や種類の異なるドメインからリンク獲得。 | 高 |
| DoFollow/NoFollow比率 | 評価されるリンク(DoFollow)としない(NoFollow)のバランス。 | 両方バランスよく獲得を目指す。 | 中 |
| リンクがページのどこに配置されているか | 記事中など目立つ場所のリンクほど効果的。 | 本文中・文脈に自然に配置されるリンクを獲得。 | 中 |
| ナチュラルリンクか | 自然に獲得したリンクかどうか。 | コンテンツの質で自然発生を促す。 | 高 |
| リンク獲得速度 | 徐々に増えるリンクの方が自然で評価されやすい。 | 急増しないよう、定期的にPR・発信。 | 高 |
| リンクタイプ | 編集者の判断で載せられるリンクは特に評価されやすい。 | 編集リンクや寄稿を意識して活動。 | 中 |
| リンク元ドメインの信頼性 | きちんと運営されているサイトからか。 | スパムサイト・リンク集からの獲得を避ける。 | 高 |
| リンクの周囲のコンテキスト | リンク前後の文章や内容が関連性を持っているか。 | リンク先の紹介文や説明も充実させる。 | 中 |
| 高権威サイトからのリンク | 特に信頼度の高いサイトからのリンク。 | 大学・公的機関・大手媒体に露出活動。 | 高 |
| 被リンクの古さ | 長期間リンクされ続けているものは信頼されやすい。 | 一度もらったリンクを長く維持する。 | 低 |
| 記事中・サイドバー・フッターのどこからか | 記事の本文中のリンクが一番評価される。 | サイドバーやフッターより本文中リンク獲得。 | 中 |
| リンク元ページの外部リンク数 | 1ページにリンクが多すぎると個々の評価が下がる。 | できれば外部リンクの少ないページから獲得。 | 低 |
| リンク配置場所 | 上部や目立つ位置のリンクは効果が高い。 | 目立つ箇所・本文上部で紹介されるように工夫。 | 低 |
| 競合が獲得している被リンク | ライバルサイトも獲得しているリンク先は狙い目。 | 競合分析ツールでリンク先を調査しアプローチ。 | 中 |
| トラフィックの多いページからのリンク | アクセス数が多いページからリンクされると評価も高い。 | 人気記事・話題記事からのリンクを獲得。 | 高 |
| 同一IPからのリンク数 | 同じサーバーばかりだと不自然。 | IPが異なるサイトからリンクをもらう。 | 低 |
| .eduや.govなど特殊なドメインからのリンク | 教育機関や政府関連は信頼度が非常に高い。 | 官公庁・大学等へのプレスリリース・連携。 | 中 |
| ソーシャルシグナル | SNSで拡散されることで間接的な評価アップにつながる。 | SNS投稿・拡散施策で話題を作る。 | 中 |
| 業界関連ブログからのリンク | 同じ業界や分野の専門ブログからのリンク。 | 専門家・業界内交流や情報提供。 | 高 |
| 編集リンク | 自分でお願いしなくても紹介されたリンクは最も評価されやすい。 | 良いサービスや記事を作り“紹介したくなる”状態に。 | 高 |
どこにリンクを貼っているのか? どこからリンクが貼られているのかもSEO対策の大切な要素です。信頼できるサイトから自然な形でもらえるリンクこそ秘訣です。
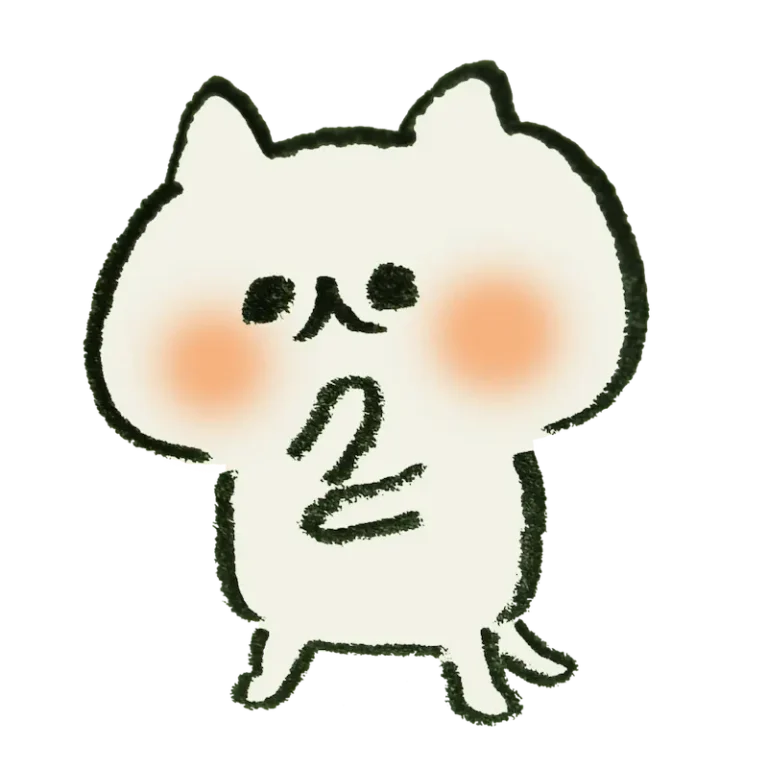
【ユーザー行動・エンゲージメント】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| クリック率検索結果が表示された回数のうち、クリックされた割合(CTR検索結果が表示された回数のうち、クリックされた割合) | 検索結果でクリックされる割合。 | 魅力的なタイトル・説明文に工夫。 | 高 |
| サイト滞在時間 | ユーザーがサイトにどれくらい長く滞在したか。 | 読み応えある記事・動画・内部リンクで伸ばす。 | 高 |
| 直帰率 | 最初のページだけ見てサイトを離れる人の割合。 | 関連記事やリンク、誘導バナーで回遊促進。 | 高 |
| セッションあたりのページ数 | 1回の訪問で何ページ見てくれているか。 | 関連・人気記事の内部リンクを強化。 | 高 |
| リピーターの割合 | 何度も訪問してくれるファンの比率。 | メルマガ・LINE・SNSなどで再訪誘導。 | 中 |
| コメント・シェア・いいね等のエンゲージメント | 記事に対するユーザーの反応や交流度合い。 | コメント欄やシェアボタン設置、キャンペーン等。 | 中 |
| モバイルユーザビリティ | スマホでも使いやすい設計か。 | モバイル対応デザイン・UIの最適化。 | 高 |
| ダイレクトトラフィック | URLを直接入力・ブックマークからの訪問。 | 名刺・広告などで直接アクセス増を狙う。 | 中 |
| コンテンツとのインタラクション | ページを下まで読んだり、画像をクリックする行動。 | 目次・図解・動画・ボタンでアクションを増やす。 | 高 |
| ブランド名での検索数 | サイト名や会社名で検索される回数。 | ブランディング強化・口コミ拡散を意識。 | 高 |
| Googleアナリティクスのエンゲージメントシグナル | Googleアナリティクスで分析される積極的な行動指標。 | 指標改善のためユーザーファースト設計。 | 中 |
| ランディングページでの行動 | 最初にアクセスしたページでのユーザー行動。 | ランディングページ最適化(CTA明確化など)。 | 高 |
| サイト内でのユーザー動線 | どの順番でページを移動したか。 | 迷わず回遊できる動線設計・CTA設置。 | 高 |
| レビュー・口コミの数 | 商品やサービスへの評価・感想の数。 | レビュー投稿依頼・キャンペーン実施。 | 中 |
| ブログコメント数 | ブログ記事へのコメントの多さ。 | コメント欄を開放し、促進コンテンツ提供。 | 低 |
| ソーシャルプルーフ | 他の人も使っているという“信頼感”の証拠。 | 導入実績・受賞歴・有名人利用の見せ方。 | 高 |
| パーソナライズされたコンテンツ | ユーザーごとに内容やおすすめを最適化。 | Cookie等でおすすめ・履歴表示を活用。 | 低 |
| 検索意図ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいか」「何をしたいか」という目的や背景との一致 | 本当に知りたかった内容と記事内容が合っているか。 | ペルソナ設定・KWリサーチ徹底。 | 高 |
| SERPへの戻り | 訪問後にすぐ検索結果へ戻る行動。 | ユーザー満足度の高い情報を一目で提供。 | 高 |
| ユーザー生成コンテンツ | コメント、投稿、写真などユーザー自身の投稿。 | キャンペーン・コンテスト等で促進。 | 中 |
| 動画の視聴時間 | サイト内動画がどれだけ長く見られているか。 | 動画の質向上・短尺と長尺の使い分け。 | 中 |
| PDFの閲覧 | PDFファイルがどれだけ読まれているか。 | PDFにも役立つ情報やダウンロード導線を設置。 | 低 |
| ページスクロールの深さ | ページのどこまで読まれたか。 | 読み進めたくなる構成・図解・ストーリー化。 | 中 |
| 強制的なインタースティシャルなし | 強制的に表示される大きな広告やポップアップが少ないこと。 | ポップアップは必要最小限・タイミング工夫。 | 高 |
| シェアしやすさ | SNSやメールで記事を簡単にシェアできる仕組み。 | シェアボタン設置・見やすい場所に配置。 | 中 |
「ユーザーが喜んでくれる」を意識して、ユーザーの助けになるヘルプフルはコンテンツを積み上げていきましょう。
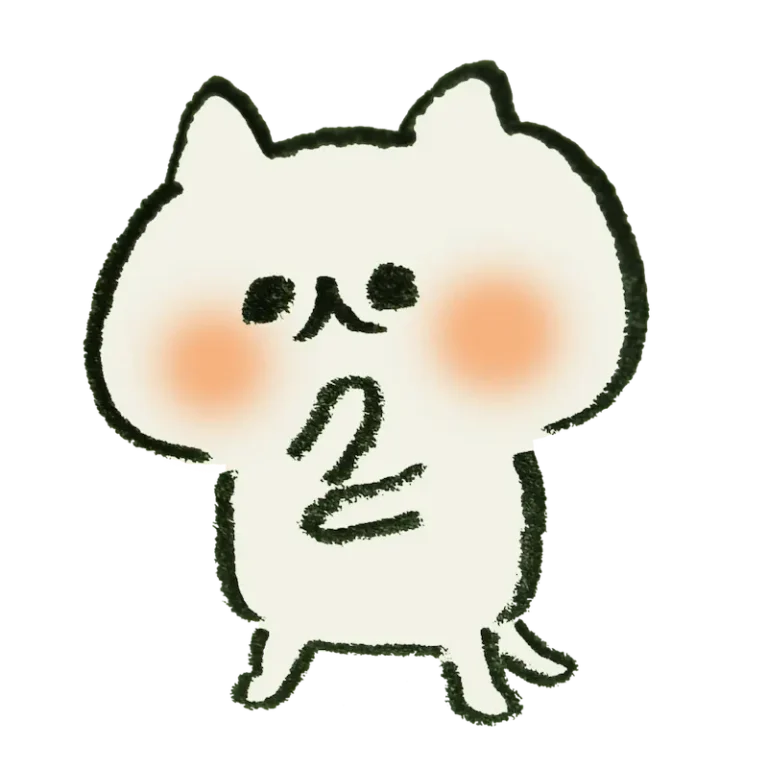
【アルゴリズム・アップデート】
| 要素(年月) | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| RankBrain(2015年10月) | AIが検索意図ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいか」「何をしたいか」という目的や背景を理解し、より良い検索結果を表示。 | ユーザーの質問や悩みに答える構成・文章にする。 | 高 |
| BERT(2019年10月) | 文脈や自然な日本語を理解するAI技術。 | 不自然な文章を避け、会話的な自然文に。 | 高 |
| コアウェブバイタル(2021年6月) | サイト速度や操作性などユーザー体験の指標。 | ページ速度・視覚安定・操作応答を最適化。 | 高 |
| モバイルファーストインデックス(2018年3月) | スマホ表示を基準にサイト評価。 | スマホ表示で見やすい・使いやすい設計を徹底。 | 高 |
| E-A-T(2014年~) | 専門性・権威性・信頼性を評価する基準。 | 著者情報・実績・出典の明示、信頼性強化。 | 高 |
| 品質評価ガイドライン(2013年~) | Googleがサイト品質を評価するルール。 | 公式ガイドを読み、運用・執筆体制見直し。 | 高 |
| パンダ(2011年2月) | 低品質・薄いコンテンツ順位を下げる。 | 独自性・網羅性のある情報を意識する。 | 高 |
| ペンギン(2012年4月) | スパムリンク対策アルゴリズム。 | 不自然なリンク・業者リンクは排除する。 | 高 |
| ハミングバード(2013年8月) | 意味全体を理解する仕組み。 | 質問形式や自然な日本語で情報をまとめる。 | 高 |
| ピジョン(2014年7月) | 地域ごと検索精度向上。 | Googleビジネスプロフィール・ローカル対策強化。 | 中 |
| Fred(2017年3月) | 広告が多すぎる・UX悪いサイトの順位を下げる。 | 広告配置は控えめに、UXを最優先。 | 高 |
| Phantom(2015年5月頃) | 主にコンテンツ品質改善のアップデート。 | 低品質・重複コンテンツを整理・削除。 | 高 |
| Medic(2018年8月) | 医療・健康分野の信頼性評価を強化。 | 信頼できる著者・監修者明記、出典明示。 | 高 |
| Possum(2016年9月) | 地域ビジネス検索の多様化。 | サービスエリア・店舗情報の最適化。 | 中 |
| Googleページエクスペリエンス(2021年6月) | UX(ユーザー体験)全体を重視。 | 使いやすいデザイン・高速表示を心がける。 | 高 |
| モバイルファーストインデックス強化(2020年7月) | モバイル対応の重要性がさらに高まった。 | モバイル画面でも情報が欠けないよう確認。 | 高 |
| リンクスパムアルゴリズム(2021年7月) | 悪質なリンクを除外し自然なリンク重視。 | 自然な形で被リンクを増やすことを重視。 | 高 |
| 商品レビューアップデート(2021年4月) | 本当に役立つレビューを優先表示。 | 実体験レビューや写真を重視。 | 高 |
| サイト品質シグナル(随時) | サイト全体の信頼性やユーザー体験を評価。 | 公式感・権威性を高める取り組みを強化。 | 高 |
| 鮮度アップデート(2011年11月) | 最新情報・新しい記事が優先表示される。 | 古い記事は定期的に内容をアップデート。 | 高 |
| ローカルサーチアルゴリズム(随時) | 地域検索の精度を高めるアップデート。 | ローカルキーワード・エリア情報の強化。 | 中 |
| トピック関連性アップデート(随時) | サイト全体のテーマ一貫性を評価。 | ジャンルを統一し、専門性を打ち出す。 | 高 |
| ブロードコアアップデート検索順位を決めるアルゴリズムを大幅に改良する「総合アップデート」(2018年3月~) | 総合的な品質・意図一致度の見直し。 | サイト全体のバランス・網羅性を意識。 | 高 |
| パッセージインデックス(2021年2月) | 記事内の一部だけでも検索評価される仕組み。 | 段落ごとに有用な情報を配置。 | 中 |
年に数回のアップデートに一喜一憂せず、地に足のついたコンテンツ作りを続けるのが一番大切です。
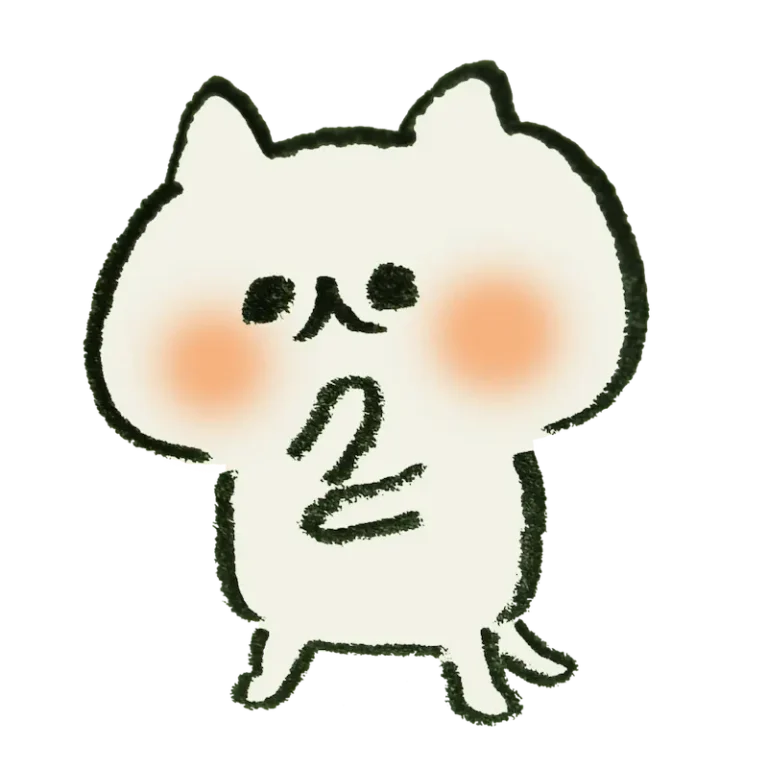
【ブランドシグナル】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| ブランド名の言及 | 他サイト・SNSでブランド名が話題になる回数。 | 業界内外でブランド名を積極的に露出。 | 高 |
| ブランド検索クエリ | ブランド名での検索回数。 | ブランド名の認知度・検索需要を高める。 | 高 |
| ソーシャルメディアでのブランド名言及 | SNSでどれだけブランド名が登場するか。 | SNS運用・キャンペーンで話題づくり。 | 高 |
| タイトルタグにブランドキーワード | ページタイトルにブランド名があるか。 | 重要ページはブランド名併記を意識。 | 中 |
| ブランドリンク | 権威あるサイトからブランドへのリンク。 | プレスリリース・業界連携で信頼獲得。 | 高 |
| 信頼性シグナル | 口コミや実績で信頼されているか。 | レビュー集めや導入事例の発信。 | 高 |
| Googleビジネスプロフィール | マップ・検索に表示される企業情報。 | 情報を常に最新・正確に保つ。 | 高 |
| ブランドレビュー | Googleや他媒体での口コミ数・質。 | ユーザーにレビュー依頼・フィードバック収集。 | 高 |
| ブランド指名トラフィック | ブランド名での流入ユーザー数。 | 広告・SNS・口コミでブランド名周知。 | 高 |
| メディア掲載 | ニュースサイトや雑誌などで紹介された実績。 | メディア露出を積極的に増やす。 | 中 |
| ドメイン権威性・信頼性 | ブランドサイト自体の信頼度。 | 被リンクや長期運用・高品質維持。 | 高 |
| ブランド引用 | 権威サイトでブランド名が紹介されたか。 | 業界団体や公的機関との協力。 | 中 |
| ローカルディレクトリでの一貫性 | 地域情報サイトや電話帳に統一した情報が掲載されているか。 | 住所・電話などを統一し、誤情報を訂正。 | 中 |
| オンライン評判管理 | ネット上の口コミや情報を管理できているか。 | 低評価対応や評判監視ツール活用。 | 高 |
| ナレッジグラフへの掲載 | Google右側にブランド情報が表示されるか。 | 公式サイト、Wikipedia、SNS連携を強化。 | 高 |
| 業界媒体での言及 | 専門メディアや業界ブログで取り上げられているか。 | 記事寄稿や取材対応を積極的に行う。 | 中 |
| スポンサー記事・広告での露出 | 有名サイトや媒体でのスポンサー露出。 | 予算に応じてタイアップ・広告出稿。 | 低 |
| ブランド名を含むURL・サブドメイン | URLにブランド名が入っているか。 | ドメイン名・サブドメイン設計を工夫。 | 低 |
| インフルエンサー・アフィリエイトリンク | 有名人やアフィリエイターによる紹介。 | コラボ企画・アフィリエイト展開。 | 中 |
| 強いソーシャルシグナル | SNSで多くシェア・コメントされているか。 | SNS投稿拡散・ユーザー参加型企画。 | 中 |
| 大手企業との提携 | 有名企業との共同プロジェクトや連携。 | 提携実績を積極的に公表。 | 中 |
| Wikipediaページ | 会社やブランドのWikipediaページがあるか。 | 正確な会社情報・実績をWikipediaに掲載。 | 中 |
| 信頼できるソースでのブランドコンテンツ | 権威性の高いメディアでブランド特集記事があるか。 | プレスリリース・取材依頼・共同研究等。 | 中 |
| ブランドキーワードからのオーガニックトラフィック | 「ブランド名+サービス名」などでの自然検索流入。 | サービス名とブランド名を一緒に訴求。 | 高 |
ブランド名で検索されるようになると、SEO的にかなり有利になります。地域や業界での“認知・知名度”を積み重ねていきましょう。
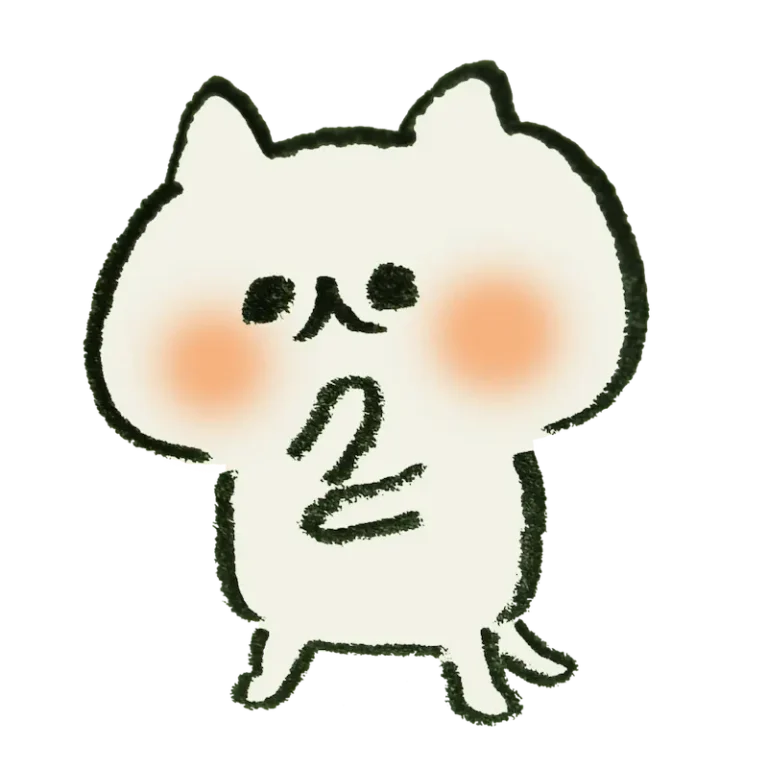
【スパム・ペナルティ要素】
| 要素 | やさしい解説 | どうすればいいのか? | 重要度 |
|---|---|---|---|
| キーワードの過剰使用 | キーワードを不自然に詰め込みすぎ。 | 自然な文脈で無理なく使う。 | 高 |
| 重複コンテンツ | 他サイトや自サイト内の重複記事。 | 重複記事を削除・正規化。 | 高 |
| 隠しテキスト・リンク | 見えない文字やリンクを仕込む行為。 | 隠し要素は使わない・削除する。 | 高 |
| クローキング | ユーザーと検索エンジンに異なる内容を見せる不正手法。 | 不正な表示切替はしない。 | 高 |
| Flashの使用 | Flashは現在評価対象外。 | HTML5等に切り替え、非対応技術は使わない。 | 中 |
| クリックベイトなタイトル | 内容と違う“釣りタイトル”で誘導。 | 内容と一致した誠実なタイトルをつける。 | 高 |
| マルウェア・セキュリティ問題 | ウイルスや不正プログラムがあるサイト。 | セキュリティ対策を徹底・定期スキャン。 | 高 |
| 薄いコンテンツ | 情報量が少なすぎて役に立たないページ。 | 網羅性・独自性あるコンテンツ制作。 | 高 |
| ファーストビューで広告過多 | 画面上部が広告だらけで本文が読みにくい。 | 広告配置を抑え、本文を最優先表示。 | 高 |
| ドアウェイページ | 誘導用の量産ページ。 | 専門性ある本質的なページを用意。 | 高 |
| 隠しリンク | 背景色と同じ色のリンクなど。 | すべてのリンクをユーザーに見せる。 | 高 |
| 不自然なリンク構築 | リンク購入や相互リンク大量取得。 | ナチュラルリンク獲得に徹する。 | 高 |
| 内部リンクの過剰操作 | サイト内で過剰にリンクを貼ること。 | 関連性・利便性を考えた内部リンクに限定。 | 中 |
| 強制ポップアップ | 強制的に開く広告や登録フォーム。 | ポップアップは控えめ&適切なタイミングで。 | 高 |
| スパムリダイレクト | 不正に検索エンジンやユーザーを別ページに飛ばす。 | リダイレクトは正規用途のみ使用。 | 高 |
| サイト目的が不明・詐欺的 | 何のためのサイトかわからない、怪しい内容。 | 明確な目的と誠実な運営を心がける。 | 高 |
| 過度なアフィリエイト | 広告やアフィリエイトリンクばかり。 | 有益なコンテンツ+適切な広告配置を守る。 | 高 |
| 無関係なコンテンツ | サイトテーマと無関係な内容の追加。 | サイトテーマを統一し、一貫性を保つ。 | 高 |
| キーワードアンカーの過剰 | 同じキーワードで大量にリンクを貼る。 | キーワードを分散し、文脈に沿ったリンク文。 | 中 |
| コンテンツファーム的なページ | 量産された質の低い記事群。 | 品質重視で記事ごとに価値を持たせる。 | 高 |
| スクレイピングコンテンツ | 他サイトから自動でコピーした記事。 | 完全オリジナル記事のみ公開。 | 高 |
| 質の低いユーザー投稿 | スパムや無価値なコメントが多い。 | 投稿やコメントのモデレーションを徹底。 | 中 |
SEOの小手先テクニックが結果的に見破られて順位が下がってしまうリスクが高いです。 SEOの王道を外さず、信頼を裏切らない運営を心がけましょう。
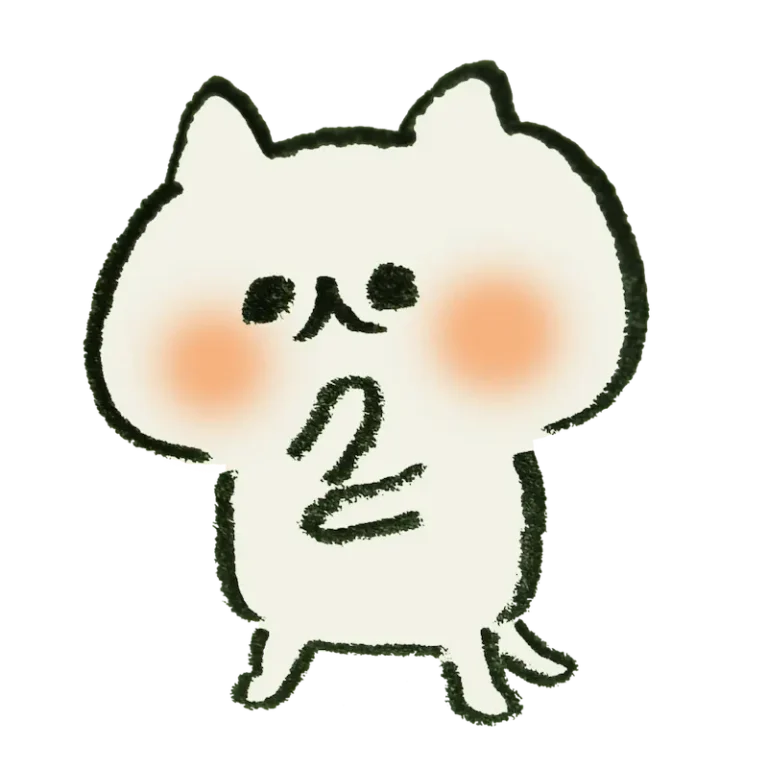
以上! 合計:202個(25+30+25+25+25+25+25+22=202)のSEOシグナルでした!
SEO対策というと、「タイトルにキーワードを入れましょう」とか、「記事は2000文字以上にしましょう」といった“テクニック”がいろいろ語られています。
でも実は、それぞれが正しいとしても、SEOは総合的な評価で決まるもの。部分的な対策だけに目を向けるのではなく、サイト全体を広い視野で見ていくことが大切です。
視野が広がるほど、Googleの本当の意図も見えてきます。
もはや「願い」と呼んでもいいかもしれませんが、Googleは“ユーザーにとって最善”を本気で目指しているのだと感じます。
200以上もの評価項目を眺めていると、Googleはただの試験官ではなく、世界中の人が自由に情報にアクセスできるように革命を起こしたリーダーなんだなと改めて思います。
だからこそ、私たちがコンテンツを作るときは、“Googleに評価されるため”ではなく、“ユーザーにとって本当に良いもの”を追求する。
それが結果的に、Googleの理念と重なり、自然とSEOにも強くなっていくと思います。